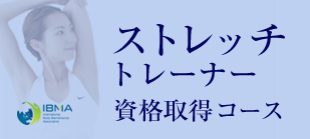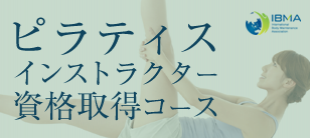- ストレッチ
- ピラティス
- トレーニング
- 肩こり・腰痛改善
ストレッチをすれば本当に怪我をしにくくなるのか?トレーニングとストレッチはどちらが大切?

2017年11月3日更新
”ストレッチをして、身体が柔らかいほど怪我をしにくい。”
そう考える方は多いのですが、実はそういうわけではありません。
筋肉が力を発揮するためには、それを生み出す土台が必要です。
上肢・下肢の筋肉が、いかにしなやかで筋力があっても、その2つを繋ぐ体幹がふにゃふにゃのゴムのようにスタビリティー(固定性)がなければ力を生み出すことはできません。
どんなに柔らかく伸びる筋肉でも、コントロールできる筋肉がないと、伸びて切れる(適切に機能しない)可能性は高くなります。
この土台となり得るのが「体幹」なのです。
体幹のインナーマッスルである腹横筋・多裂筋・横隔膜・骨盤底筋群がそれに当たります。
つまり、四肢の動きを最大に発揮させるためにも、体幹インナーマッスルのスタビリティー(固定性)が重要なのです。
関節可動域を制限していると思われる筋肉をストレッチしているのに、あまり変化が見られないといった経験をしている方は少なくないのではないでしょうか?
スタティックストレッチと呼ばれるような、関節稼働域を拡げるためのシンプルなストレッチだけではなかなか効果が引き出せない場合、ストレッチで効果を出せない原因が、
① 筋肉の「柔軟性」からくる問題
② 筋肉の「固定性」からくる問題
なのかを見極めることで、より簡単にアプローチすることが可能になります。
もし制限が、①(筋肉の「柔軟性」からくる問題)であれば、様々なストレッチのテクニックを使って可動性を拡げることが効果的となります。
例えば、「PNFストレッチ」や「相反性抑制」、「運動反射」等は、筋肉の反応をより効果的に引き出す事ができ、硬くなっている筋肉の柔軟性を改善することが期待できます。
しかし、思うような可動域の改善が見られない場合、その筋肉が付着している関節の柔軟性が十分にあるかどうかもチェックしてみましょう。
もし、関節そのものに可動域制限が見つかった場合、ストレッチ以外のアプローチ方法(関節モビライゼーションなどの関節に直接アプローチするテクニック)が柔軟性を回復させるための鍵となります。つまり、このような場合は、従来のストレッチだけで大きな効果を得ることは難しいということです。
関節可動域の制限において、②(筋肉の「固定性」からくる問題)が関わっている場合、関節可動域を拡げる為に、従来のストレッチとは少し異なるアプローチが必要となります。まず、固定性の問題について簡単に解説させて頂きます。
身体の「柔軟性」は、基本的に「固定性」があって成り立っています。身体を支える土台、つまり「固定性」がうまく働かないと「柔軟性」にも大きな影響を及ぼすのです。
筋力トレーニングにおいて、この考え方は一般的なのですが、この考え方は、ストレッチの効果を引き出す時においてもとても重要です。
例えば、ハムストリングのストレッチで関節可動域に制限を感じた場合、「柔軟性」の問題にアプローチしてもあまり改善が得られなかったとします。この場合は、「固定性」の問題の可能性があると判断し、お腹周りを安定させるようなアプローチを取り入れてみましょう。「両手で壁を押す」「軽いダンベルを手で持ち上げてその状態をキープする」「固定されたチューブを引っ張ったままキープする」などといった運動です。
こうして身体の末端にアイソメトリック収縮を加えることにより、ハムストリングを伸ばすための土台である身体の中心部が安定し、ハムストリングはより大きな可動域を発揮しやすくなるのです。言い換えると、腹部を安定させて可動域の改善が見られた場合、可動域の問題は「柔軟性」ではなく「固定性」の問題が大きく影響していたと考えることが出来ます。
もちろん、「柔軟性」と「固定性」の両方が、関節可動域に影響していることもあるので、2つの要素を同時にアプローチすることも可能です。
例えば、背臥位(あおむけ)のストレッチで、ダンベルを片手で天井に向かって持ち上げてキープした状態で、硬い側のハムストリングをストレッチします。この時のストレッチ方法は、静的ストレッチでも、動的ストレッチでも構いません。「柔軟性」と「固定性」両方にアプローチすることによって、よりストレッチ効果は期待できます。
このように、シンプルなスタティックストレッチだけで効果を引き出せない場合、①(柔軟性からくる問題)なのか、②(固定性からくる問題)なのかを分けて考える事で、よりパーソナライズされたストレッチを提供できるようになるでしょう。
人間は二足歩行の動物なので、やはり最終的には二足歩行、そして動きの中でこの体幹のスタビリティー(固定性)を発揮しなければなりません。
背臥位、四つ這い、膝立ち、立位の順で、徐々に体幹トレーニングの強度を上げていくことが望ましいでしょう。
例えば、スクワットを行う際に、ふくらはぎの筋肉が硬くてうまく下にしゃがめなかったから、ふくらはぎを柔らかくする為に壁に手をつき、体重を前方にかけてふくらはぎのストレッチをしたとします。このストレッチをすることでスクワットができるようになるかというと、そうではありません。
なぜならば、壁に手をついて前方に体重をかけるふくらはぎのストレッチと、スクワットのしゃがみ動作でストレッチされるふくらはぎの筋肉のパターンは全く別物だからです。
スクワットのしゃがみをスムーズにするためにふくらはぎの柔軟性を高めるのであれば、スクワットの動作と同じ肢位、パターンでのストレッチをしないと身体が適応してこないのです。
このように、目的とする動作に合ったトレーニングをおこなう事をトレーニング用語で「特異性の法則」といいます。
他にも、腰痛を訴える方が、デスクワークでほぼ座った状態であるならば、目標は座位での体幹インナーマッスルのスタビリティーの確保であり、必ずしも立位だけのトレーニングで腰痛に適応するわけではありません。
スポーツパフォーマンスにおける動作でも同様で、ゴルフのスイングで体幹が不安定になるのであれば、回旋動作での体幹インナーマッスルのスタビリティーを確保しなければなりません。
巷には様々なメソッドが溢れています。
同じトレーニング方法を万人に当てはめることはとても簡単ですが、本来はどんな動作におけるスタビリティーを求めているかを見極めるということが大切なのです。
関節は、お互いが密接に関係していて、基本的に動きは「連鎖」しています。
例えば、骨盤が前傾になれば、大腿骨は内旋位(内向き)になり、下腿(脛骨)は外旋(外向き)しやすくなります。骨盤が後傾になると、逆に大腿骨は外旋位(外向き)になり、下腿(脛骨)は内旋(内向き)しやすくなります。
また、関節各々でモビリティー(可動性)は異なります。
この「連鎖」や「モビリティー」を考慮して、トレーニング計画を立てることは、スポーツパフォーマンスだけでなく日常生活のクオリティを上げるという意味でも重要になってきます。
例えば「腰が痛い」という症状を訴える方がいます。
この痛みは本当に腰が原因なのでしょうか?
確かに外傷の場合はそうかもしれませんが、必ずしも痛みの箇所が、原因になっているとは限りません。周囲の関節のモビリティーからきている場合も多いのです。
関節は、構造によって、ある程度可動域が決められています。足関節はモビリティーがあり、膝関節はあまりなく、股関節はあり、腰部はない、といった構造になっています。
まず、股関節の柔軟性をチェックしてみてください。
腰痛の原因が股関節の柔軟性の低下からきているというケースは決して少なくありません。
関節はお互いがその動きを補いやすいので、股関節が硬く動かないのであれば、そのぶん、腰部を過剰に動かしてしまうことで、腰部がスタビリティー(固定性)を失い、痛みとなって現れてくるのです。
この場合、いかに股関節を動かしながらトレーニングを行えるかを考える必要があります。
関節の「連鎖」や「モビリティー」を考慮したトレーニングをすることで、腰痛の改善効果が期待できるのです。
ただし、ここで気をつけて頂きたいのが、関節のモビリティー(可動性)にも癖があるということです。
「動きすぎる関節」があるということは、その代償として「動きがない関節」があるという可能性が考えられます。
例えば、股関節のモビリティーをみる場合、ある一方向においてモビリティーが優れていたとしても、必ずしも他の方向にもモビリティーが充分にあるとは限らないということです。関節まわりの軟部組織は、ストレスに順応する習性がありますから、もし日常生活やストレッチ、トレーニングで、ある特定の方向にしか関節を動かさない場合、動かされない方向の関節はモビリティーが失われます。
自分の好きなストレッチやトレーニングばかり行っていると、関節のアンバランスを生み、痛みの原因となる可能性があるのです。
けがの予防としてストレッチに取り組んでいるのに、逆に身体の特定の箇所を過剰に使わせて、痛みの原因を作ってしまっては本末転倒です。
バランス良くストレッチやトレーニングをすることが大切です。
アスリートが、オフシーズンに異なるスポーツの動きを取り入れることがありますが、これは専門のスポーツ動作で偏った筋肉のストレスに対して、全く異なった動きを要求されるスポーツをすることにより、普段使われにくい筋群を刺激しながら身体のバランスを保ち、なおかつ有酸素能力を維持するためなのです。
スタビリティー(固定性)とモビリティー(可動性)の関係性を考えると、どちらも大切であることがわかります。
つまりスタビリティー(固定性)を高めるためのトレーニングばかりしていたり、モビリティー(可動性)を高めるためのストレッチばかりしていてもダメなのです。
ストレッチだけしていても、怪我をしにくくなるとは言えないのです。
例えば、
コンディショニングを整えているのに「痛みが消えない」「機能が改善しない」
トレーニングをしているのに「長く続かない」「パフォーマンスが上がらない」
といったことが起こり得るのですが、
この場合、大抵どちらかの要素に偏りすぎていて、どちらかの要素が不足しています。
コンディショニングは、身体の”環境作り”であり、
トレーニングは、”コンディショニングで整えた環境を土台として身体を鍛え、強化していくこと”です。
自転車の前輪と後輪をイメージして下さい。
前輪がコンディショニングの要素、後輪がトレーニングの要素だとしましょう。
トレーニングをどんなに頑張って行っても、コンディショニングが整っていなければ、大きい後輪(トレーニング)に比べて前輪(コンディショニング)が小さすぎてうまく走ることはできません。
逆に、前輪(コンディショニング)が大きい状態、つまりコンディショニングが完璧な状態でも後輪(トレーニング)となる筋力やトレーニング能力が低ければ、これもまたうまく自転車を走らせることはできません。
この2つのバランスがかみ合って初めて真っすぐ自転車を走らせることができるのです。
例として、高齢者の方のトレーニングやリハビリは肉体的にも精神的にも負担となりやすく、継続的にトレーニングを行いたくても大抵の場合続きません。
この大きな原因の1つとして、コンディショニング、つまり痛みや身体の柔軟性など、身体の環境が整っていないことが挙げられます。
トレーニングをする意志や気持ちがあったとしても、身体のコンディションが低ければトレーニングに対する身体の負担が強すぎて精神的にも肉体的にも苦痛となってしまうのです。
こういった場合はトレーニングのみに注意を向けるのではなく、それを可能にする身体の環境作り、つまりストレッチやリリース等のコンディショニングアプローチに一度目を向けてみましょう。
しかし、忘れてほしくないのは身体の動き(パフォーマンス)を可能にするのは筋であり、これを最大限生かすには筋力トレーニングが不可欠だということです。
いくらコンディショニングが良くても、それを発揮するだけの筋力がなければ競技で優位に立つ事も、日常生活動作を向上させることも不可能です。
アスリートにとって筋量・筋力はとても重要であり、例えばコンタクトスポーツにおいて同じ体重の2人がぶつかった場合、確実に筋量が多い方が有利となりますし、一般の方々においても筋や筋力がなければ快適な日常生活を送ることはできません。
・関節稼働域の制限が、筋肉の「柔軟性」からくる問題であれば、様々なストレッチテクニックで効果が期待できる
・身体の「柔軟性」は、「固定性」があってこそ成り立っているので固定性を高めるトレーニングも必要
・ストレッチ効果を高めるために、柔軟性からくる問題なのか、固定性からくる問題なのかを分けて考える必要がある
・トレーニングとコンディショニングは、別のものとして考える
・コンディショニングは、身体の”環境作り”であり、トレーニングは、”コンディショニングで整えた環境を土台として身体を鍛え、強化していくこと”
・トレーニングとコンディショニングは両輪であり、両者のバランスが整っていることが大切
ストレッチをしていれば、やわらかくなる(関節稼働域が拡がる)と考えているストレッチトレーナーの方は多いようです。
しかし、スタティックストレッチだけをしていれば、全ての方に効果が得られるとは限らないのです。
どの運動パフォーマンスにおいても「スタビリティー(固定性)」と「モビリティー(可動性)」とを作ることが大切になります。
ストレッチをすることで、怪我をしにくくなることもまた事実ですが、ストレッチだけをしていれば怪我がしにくくなるわけではありません。
「スタビリティー(固定性)」と「モビリティー(可動性)」の両面から、ストレッチやトレーニング計画を組み立てていくことをおすすめします。
「トレーニング」と「コンディショニング」を異なる要素として捉え、その方に足りないものは何かをしっかりと見極めることです。
コンディションを整えて身体の環境が良ければ運動を続けるモチベーションも保ちやすくなりますし、適切なトレーニングで筋・筋力がつけば様々な場面で動きやすい身体を作る事ができるでしょう。
[ストレッチをもっと深く学ぶ!]
IBMA認定パーソナルストレッチトレーナー資格スクール
[ストレッチの上位資格「パーソナルトレーナー」を目指す方は]
IBMA認定パーソナルトレーナー資格取得コース
[参考ブログ記事]
アスリートがトレーニングで考慮すべき3つのこと

監修者
IBMA(国際ボディメンテナンス協会)
[公式HP]http://ibma.asia/
ボディメンテナンスに関する様々な資格の認定事業を行い、確かな知識と技術を持った専門家を育成。
今後はアジア各国を中心とした啓蒙活動も視野に入れ、国際的な格調ある資格団体を目指している。
様々なボディメンテナンスの現場に携わる専門家を育成し、相互研鑽を通じて専門性を高め、世界にセルフメンテナンスの普及を図り、社会貢献していくことを目的としている。
[主な認定資格]
・IBMA認定ヨガインストラクター資格
・IBMA認定ピラティスインストラクター資格
・IBMA認定パーソナルストレッチトレーナー資格
・IBMA認定パーソナルトレーナー資格
・IBMA認定タイ古式マッサージセラピスト資格
こちらのブログ記事もおすすめ
最新ブログ記事
ストレッチ の動画講座を見る
- すべてのブログ記事一覧
- ヨガ
- ピラティス
- ストレッチ
- タイ古式マッサージ・マッサージ
- 加圧トレーニング
- トレーニング
- 整体・姿勢改善
- 肩こり・腰痛改善
- ツールトレーニング
- ダイエット
- 糖質制限
- 解剖学
- アロマテラピー
- トレーナー・インストラクター
- 独立開業・起業・ビジネス
- 資格・スクール
- 資格スクールレポート
- ワークショップレポート
- パーソナルトレーニングジム・ダイエットジム
- ヨガスタジオ(常温ヨガ・ホットヨガ)
- ヨガインストラクターRYT200資格スクール

監修者
IBMA(国際ボディメンテナンス協会)
[公式HP]http://ibma.asia/
ボディメンテナンスに関する様々な資格の認定事業を行い、確かな知識と技術を持った専門家を育成。
今後はアジア各国を中心とした啓蒙活動も視野に入れ、国際的な格調ある資格団体を目指している。
様々なボディメンテナンスの現場に携わる専門家を育成し、相互研鑽を通じて専門性を高め、世界にセルフメンテナンスの普及を図り、社会貢献していくことを目的としている。
[主な認定資格]
・IBMA認定ヨガインストラクター資格
・IBMA認定ピラティスインストラクター資格
・IBMA認定パーソナルストレッチトレーナー資格
・IBMA認定パーソナルトレーナー資格
・IBMA認定タイ古式マッサージセラピスト資格